吹奏楽の起源は軍楽隊|行進曲から広がった音楽の世界 【吹奏楽まめちしき】 #4
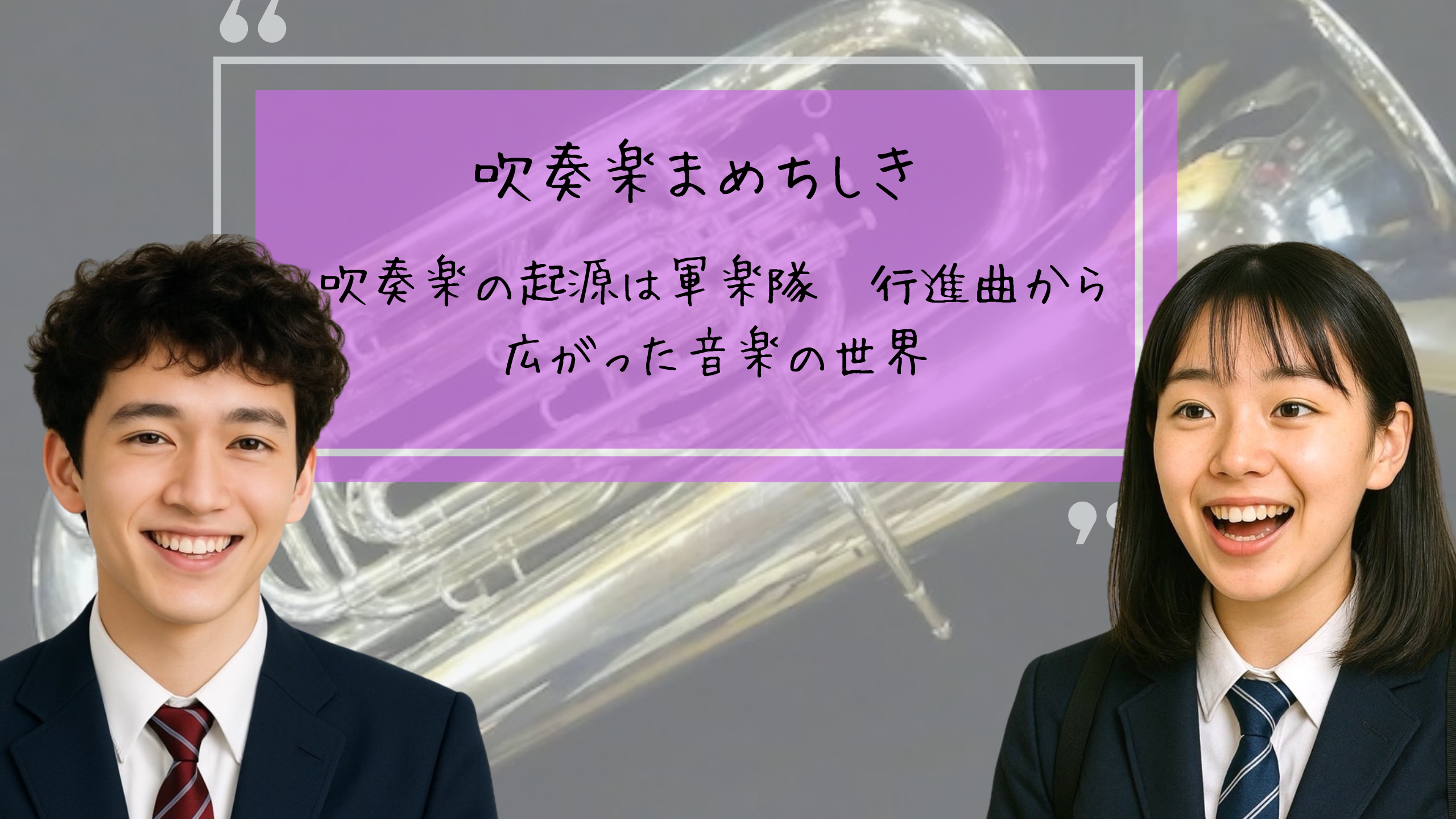
 柚葉
柚葉先輩、なんで吹奏楽部って行進曲ばっかりやるんですか?



いい質問だな。実は吹奏楽の始まりは“軍楽隊”なんだ。



軍楽隊? それって兵隊さんの音楽ってことですか?



そうそう。歩調を合わせるリズムと士気高揚の旋律…つまり“戦場版BGM”ってわけだ!



先輩、言い方オタクすぎますよ…!
吹奏楽の起源は軍楽隊|行進曲から広がった音楽の世界
「吹奏楽部といえば行進曲!」というイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。実際、吹奏楽部では運動会や式典、コンクールでも行進曲を演奏する機会が少なくありません。
なぜ吹奏楽と行進曲は切っても切り離せない関係にあるのでしょうか?
その答えは、吹奏楽のルーツにある 軍楽隊 にあります。
吹奏楽の始まりは軍隊から
吹奏楽の起源は、ヨーロッパの軍楽隊にさかのぼります。
まだ電子機器もスピーカーもなかった時代、戦場で遠くまで音を伝える手段は「楽器」でした。太鼓やラッパは、兵士たちに行進の合図や戦闘の開始を知らせるために欠かせない存在だったのです。
例えば、太鼓の「ドンドン」というリズムは歩調を合わせるのに最適で、ラッパの鋭い音は戦場の喧騒の中でもはっきりと聞こえました。つまり、軍楽隊は音楽隊であると同時に「通信手段」でもあったのです。


行進曲が生まれた理由
軍楽隊の役割は兵士の士気を高めることにもありました。規則正しいリズムと勇ましい旋律は、兵士たちの心を鼓舞し、戦場へ向かう緊張を和らげる効果があったといわれています。
そのため「行進曲(マーチ)」は、軍楽隊から自然に生まれた音楽の形式でした。一定のテンポと明快なリズムを持つ行進曲は、行進にも、士気を高める音楽としてもピッタリだったのです。
今日でも有名な「星条旗よ永遠なれ(Sousa)」や「ワシントン・ポスト」などは、当時の軍楽隊文化の象徴ともいえる作品です。
軍楽隊から市民へ、そして学校へ
19世紀になると、軍楽隊の文化は次第に市民社会へ広がっていきます。地域のお祭りや式典で演奏する市民バンドが生まれ、軍事目的を超えて「音楽を楽しむ」活動へと変化していきました。
日本では、明治時代に西洋音楽が導入された際、まず軍楽隊を通じて広まったといわれています。陸軍・海軍には専属の音楽隊があり、そこで使われた楽譜や楽器が教育現場にも取り入れられました。
これがやがて、現在の中学・高校の吹奏楽部へと発展していったのです。
吹奏楽の多彩なレパートリーへ
もちろん現代の吹奏楽は、行進曲だけではありません。クラシックの名曲を編曲した作品や、ジャズ、ポップス、映画音楽、さらには吹奏楽オリジナルのシンフォニック作品まで幅広く演奏されます。
とはいえ、行進曲はいまもなお吹奏楽の“顔”ともいえる存在です。運動会や式典で演奏されると自然と空気が引き締まり、誰もが歩調を合わせたくなる…これは軍楽隊から続くDNAといえるでしょう。


行進曲を演奏するときに感じたいこと
普段の部活で行進曲を練習するとき、つい「単純で簡単な曲」と思いがちかもしれません。
でも、行進曲には数百年にわたる歴史と役割が詰まっています。かつて兵士がその音に合わせて歩き、心を鼓舞していたことを想像すると、同じ曲でも違った響き方がしてくるはずです。
「どうしてこんなに規則正しいんだろう?」
「どうしてこんなに勇ましいんだろう?」
そう思ったときこそ、吹奏楽のルーツを感じるチャンスです。
まとめ
吹奏楽の起源は軍楽隊。そこから生まれた行進曲は、今も吹奏楽に欠かせない大切なジャンルです。
軍楽隊が果たした役割を知ることで、私たちが演奏する行進曲が単なる「曲」ではなく、歴史を背負った音楽であることに気づけます。
次に行進曲を演奏するときは、ぜひその背景を思い浮かべながら吹いてみてください。きっと、今までとは少し違った音楽の世界が広がるはずです。



なるほど~!行進曲って、ただの曲じゃなくて歴史が詰まってるんですね!



そうだな。ルーツを知ると、演奏する気持ちも変わるんだ。



じゃあ今度の練習で、歴史を意識して吹いてみます!



いい心がけだな。きっと音に深みが出るはずだぞ。
\吹奏楽のこと、ぜんぶここに /
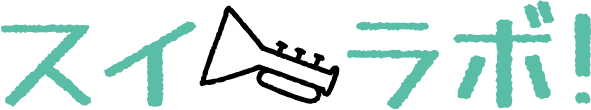

コメント