吹奏楽の未来を地域とつなぐ――ヤマハが取り組む「地域展開」支援のかたち|スイラボスペシャルインタビュー
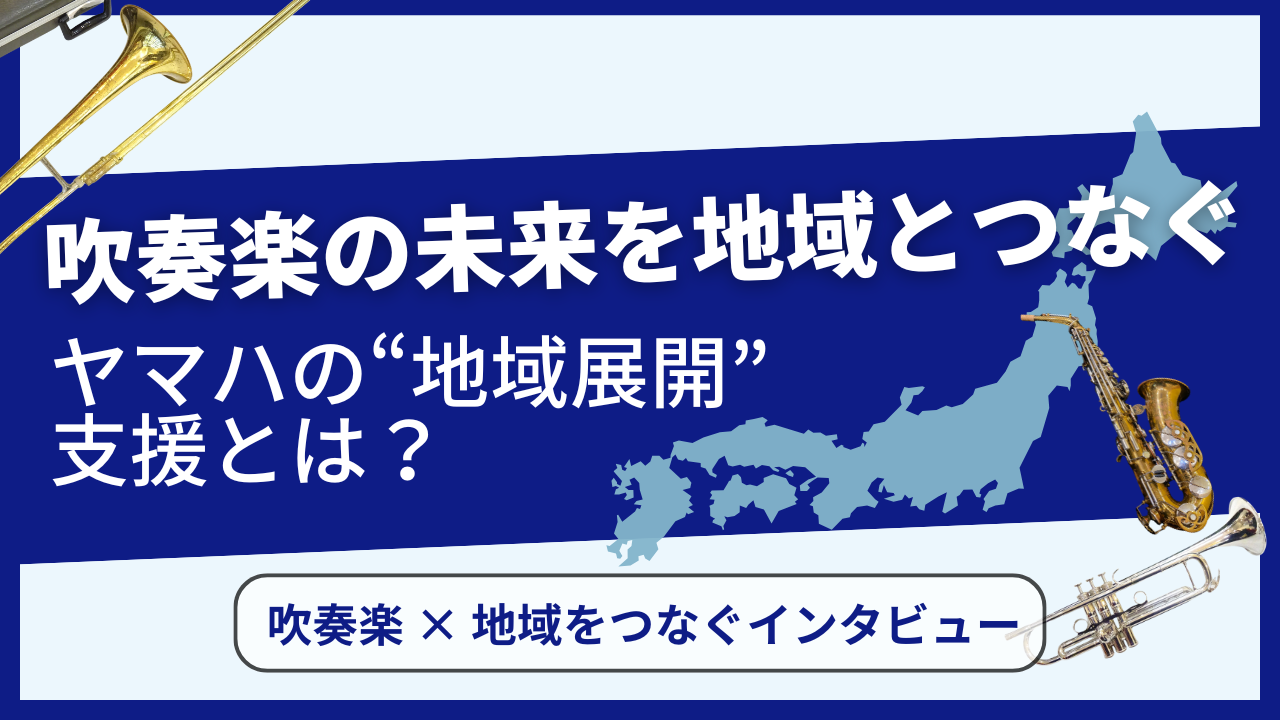
🎷はじめに
いま、全国の学校で進められている「部活動の地域展開」。
これは文部科学省が進めている取り組みで、学校と地域が協力して、子どもたちが地域の中で安心して活動を続けられる環境を整えることを目的としています。
吹奏楽の分野は、楽器の管理や練習場所、指導してくれる人など、必要な条件が多く、地域化が難しい分野のひとつとされています。
だからこそ今、企業・自治体・地域団体が協力し合い、「どうすれば音楽を続けられる場を守れるか」を考えることが大切です。
ヤマハミュージックジャパンは、そんな地域展開の流れの中で、学校や地域を支える仕組みづくりに取り組んでいます。
今回は、ヤマハミュージックジャパンの皆さんに、吹奏楽を取り巻く現状と、地域に寄り添う活動についてお話を伺いました。
お話をしてくれた人
株式会社ヤマハミュージックジャパン 管弦打事業戦略部 普及課 加藤 幸平さん(以下加藤と表記)
株式会社ヤマハミュージックジャパン 管弦打事業戦略部 普及課 須合 弘明さん(以下須合と表記)
インタビューした人
スイラボ編集部 富石祐子(以下富石と表記)
🎵吹奏楽の現場はいま、どんな課題がある?
富石 まず、吹奏楽の現場でいまどんな課題があるとお考えですか。
加藤 一番大切なのは、「活動の場を減らさないこと」です。
吹奏楽は「人・物・お金」の3つが同時に関わってくる分野です。
指導してくれる人がいて、楽器や練習できる場所があり、そして移動や運営に必要なお金がある。
そのすべてが整って初めて、日々の練習や発表が成り立ちます。
須合 少子化の影響で、1校あたりの部員数が減っているのも大きな課題です。
「無理のない運営」をどう設計するかが大切になってきます。

🌱学校と地域が“チーム”になる「地域展開」
富石 「地域展開」という言葉がキーワードになっていますが、どういった考え方だと思いますか?
加藤 「地域展開」というのは、学校の外に部活動を“移す”というより、学校・保護者・地域がチームになって活動を広げていくという考え方です。
学校の備品や校舎を地域で共有したり、自治体や企業が協力したり。
地域の実情に合わせて、子どもたちが音楽を続けられるような形を、一緒に作っていきましょうということですね。
👩🏫指導者を育て、支える仕組み
富石 どんな人が指導するのかという、指導者の確保や育成も重要なテーマですよね。
加藤 はい。ヤマハには全国で約500名の登録インストラクターがいます。
まずは子どもたちと関わる上で欠かせない、安全やコンプライアンス(法令遵守)に関する研修をしっかり行っています。
大学の先生方を招いて講座を受けることもあります。
また、技術的な指導の価値をきちんと見える形にし、指導料や時給の適正化について自治体や学校に丁寧に説明しています。
「鍵開けや見守り」と「専門的な技術指導」は役割が違うからこそ、その違いを理解してもらうことが大切です。
ヤマハは人材派遣業ではありません。
育成した指導者が地域で活動できるよう、地元の楽器店や法人と連携し、橋渡し役として支援しています。
💻オンラインでつながる、新しい指導の形
富石 オンラインでの指導も増えているそうですね。
加藤 はい、最近は手応えを感じています。
たとえば北海道の空知地区では、合同部活でコンクールに挑戦する生徒たちをオンラインでサポートしました。
大阪府内でも、1人の講師が複数校をオンラインで担当する取り組みが進んでいます。
「画面越しでも見てもらえてうれしい」「姿勢や音の出し方のアドバイスが的確」といった声も多く、
オンラインの良さを活かした新しい形が広がっています。
🌐地域の情報をつなぐ「地域展開ナビ」
富石 学校や自治体、地域の団体など――吹奏楽の活動をつなぐ情報発信については、どんな取り組みをされていますか?
加藤 はい。ヤマハでは、全国の事例を紹介するウェブサイト「地域展開ナビ」を運営しています。
このサイトでは、地域ごとの取り組みや成功のヒント、現場の声などをわかりやすくまとめています。
たとえば「どんな形で地域バンドが学校と連携しているか」「自治体がどんな支援を行っているか」など、実際の事例を具体的に紹介する場所なんです。
また、SNSでは「#地域展開の風」というハッシュタグを使って、演奏会の告知や部員募集、指導者募集などの情報をシェアしています。
“地域展開の風”という名前には、「それぞれの地域で吹く小さな風が、全国でつながって大きな流れになるように」という願いが込められています。
こうした情報発信を通して、私たちが目指しているのは「地域の中で音楽の循環を生むこと」です。
ある地域の取組が他の地域の刺激になり、「じゃあうちでもやってみよう」と次の動きにつながる。
そのきっかけを作れるのが“見える化”の力だと思っています。
実際に、ナビで紹介された取り組みを見て連絡を取り合い、地域同士で新しい交流が生まれたケースもあるんですよ。
地域展開は“制度”ではなく“人と人とのつながり”から育っていくもの。
だからこそ、情報を開いて共有していくことがとても大切なんです。
地域展開ナビはこちらから!https://jp.yamaha.com/services/music_pal/suibunavi/chiikiikounavi/index.html
🎶世代を越えて合奏を楽しむ場づくり
富石 孫と一緒に吹奏楽!という、多世代で楽しむ取り組みも進めていると伺いました。
加藤 はい。「ブラバンデー」や「ブラスジャンボリー」といったイベントを全国各地で開催しています。
学生時代に吹いていたきり、クローゼットの奥に眠らせている楽器をもう一度演奏したいという方が、年に1〜2回でも合奏を楽しめるような場ですね。
将来的には、中高生や地域の大人が一緒に吹けるような、“世代を越えた合奏の場”に育てていきたいと考えています。

🧩地域の中で“教える人”を増やす
富石 指導者不足への対応も大きな課題ですね。どんな取り組みをお考えですか?
須合 地域の経験者や保護者、教育学部の学生など、指導や運営に関わっていただける方がいらっしゃる地域があれば、ヤマハのインストラクターが「指導法そのもの」を教える講座を検討しています。
地域の中で“教えられる人”を増やしていくことが、長く続けるための大切なポイントですね。
🎵文化をつなぎ、未来へ広げる
富石 吹奏楽文化の継承という点では、どんなことをお考えですか?
須合 少子化の影響で、小規模な編成が増える一方で、吹奏楽連盟が合同部活での出場を認めるようになったため
大人数での合奏が経験できるチャンスでもあります。
加藤 これから5〜10年のうちに、
①学校の中で高みを目指す“スクールバンド”と、
②地域で世代を超えて楽しむ“コミュニティバンド”、
この二つの流れが進むと思います。
ヤマハはその両方を支える仕組みを整えていきたいですね。
🎹小学校からつなぐ「出会い→継続→広がり」
加藤 小学校での鍵盤ハーモニカやリコーダーは、吹奏楽への入口です。
小さいころの“楽器との出会い”から、中学・高校・地域へと続く流れを、無理のない形で作っていきたい。
「出会い→継続→広がり」というサイクルを、みんなで支えていけたらと思っています。
💬最後に――地域で活動する皆さんへ
加藤 目指していることは、きっと同じだと思います。
やり方や立場が違っても、「子どもたちが音楽を続けられる場所を守りたい」という気持ちは共通です。
お互いに知恵を出し合い、ときには助け合いながら、吹奏楽の輪を広げていけたらうれしいです。
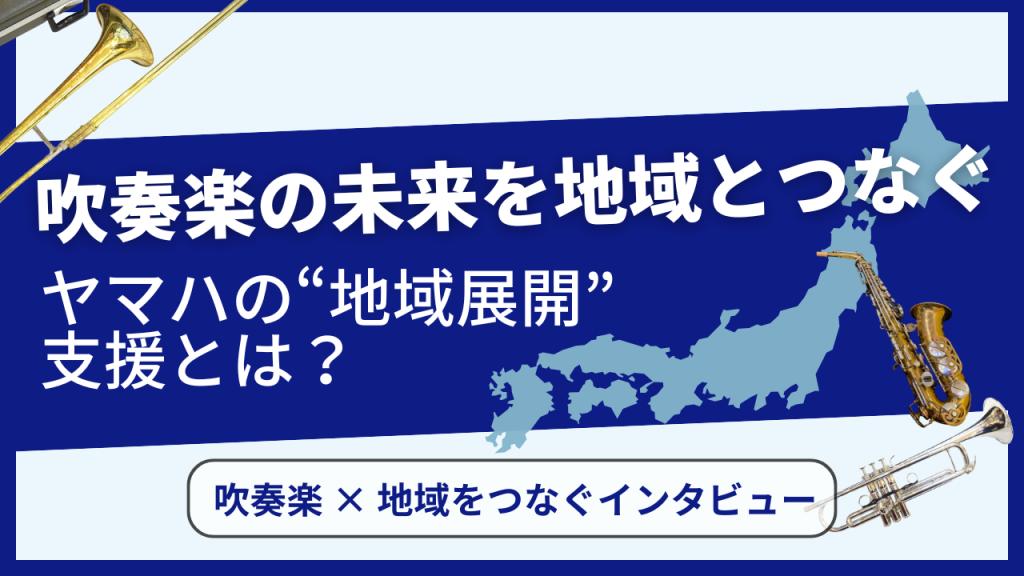
取材協力(敬称略)
株式会社ヤマハミュージックジャパン 管弦打事業戦略部 普及課 加藤 幸平
株式会社ヤマハミュージックジャパン 管弦打事業戦略部 普及課 須合 弘明
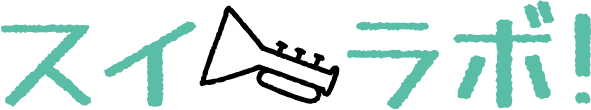

コメント