楽器の裏側へようこそ!リペアマンが語る修理現場の裏話
🎼 修理工房には小さなドラマがある
「楽器の修理」と聞くと、壊れた部品を直すだけの作業をイメージする方が多いかもしれません。
でも実際の修理工房は、ただの作業場ではなく、日々さまざまな“ドラマ”が繰り広げられる場所です。
笑える話、驚く話、そして心が温まる話――。
今日はそんな リペアマンだけが知る修理現場の裏話 をご紹介します。
🛠️ ケースを開けたら大冒険
長い間使われずに眠っていた楽器を持ち込まれることは少なくありません。
「学生の頃に吹いて以来30年ぶりにケースを開けました」という方もいらっしゃいます。
ケースを開けた瞬間に広がるのは、楽器の歴史そのもの。
中には思わず声をあげてしまう光景も…
- キーの隙間にびっしりと生えたカビ
- 底に砕けたリードが何十枚も積もっている
- お菓子の袋や消しゴムのカスと一緒に楽器が眠っている
修理を始める前に「発掘作業」から入ることもあり、タイムカプセルを開けるような瞬間に立ち会えるのもリペアマンならではです。

🎵 「壊れてます!」と思ったら…
「音が出なくなった!」「もう壊れてしまったのかも…」と駆け込まれるお客様も多いですが、調べてみると原因は意外と単純なことがあります。
- マウスピースがしっかり差し込まれていなかった
- コルクグリスを塗らずジョイントが固まっていただけ
- サックスのバネが外れていただけ
演奏者にとっては“大事件”でも、工房では“数分の調整”であっさり解決。
修理後に「えっ、これだけで!?」と驚かれる表情を見るのは、工房での密かな楽しみでもあります。
🎶 修理で蘇る“あの頃の音”
ある日、学生時代に吹いていたクラリネットを持ち込まれたお客様がいました。
タンポは劣化してボロボロ、管体はくすんで音もスカスカ。
「もう吹けないかも」と心配されていましたが、丁寧にタンポを交換し、ジョイントを調整、管体をクリーニングすると…。
吹いた瞬間に「懐かしい!」と声を上げられました。
「当時の音が戻った」と感動し、目を潤ませていたのが印象的でした。
修理はただ部品を直すだけでなく、思い出の音を蘇らせる時間旅行でもあるのです。

🎷 工房に舞い込む意外な出来事
修理現場では、時に予想外の出来事に出会うこともあります。
- タンポの下から出てきたティッシュ
「息漏れがする」と持ち込まれた楽器を分解したら、タンポの下からティッシュの切れ端が…。練習中に応急処置で入れたものがそのまま固まっていたケースです。 - ケース内に飲み物をこぼしてベタベタに
お茶やジュースがこぼれて、管の中から甘い匂いが漂ってくることも。内部がベタついてキーが動かなくなり、徹底クリーニングが必要になることがあります。 - 虫食いでコルクがボロボロに
長期間放置された木管楽器では、ジョイントコルクが虫にかじられてボロボロになっていることも。修理だけでなく殺菌処理や部品交換まで必要になる、ちょっとショッキングなケースです。
演奏者にとっては「まさか!」という出来事も、工房にとっては「よくあるある」。
それぞれの楽器に、持ち主の生活や歴史がにじみ出ている瞬間でもあります。

🌟 裏話が教えてくれること
こうした修理現場のエピソードからわかるのは、
楽器は壊れたら終わりではなく、修理で再び命を吹き込める存在 だということ。
- 楽器を清潔に保つ大切さ
- ちょっとした不調でも早めに点検へ出す安心感
- 修理によって思い出や音楽が蘇る喜び
楽器は単なる道具ではなく、奏者の歴史や思いを宿した相棒。
だからこそ、修理を通じて新しいステージへとつながっていくのです。
🎼 まとめ
修理工房は、単なる作業場ではありません。
そこには笑いも驚きも感動も詰まった“音楽の裏舞台”があります。
「音が出にくい」「調子が悪い」そんな時はもちろん、
「ちょっと気になるな…」という時でも気軽に訪ねてください。
あなたの楽器にも、まだ見ぬドラマが眠っているかもしれません。

この記事の著者
管楽器リペアマン
服部 悟
服部 悟
岡山県出身。10代の頃より吹奏楽に親しみ、専門学校卒業後、楽器店勤務を経て独立。
2000年代より本格的に管楽器修理・販売・教育事業に携わり、現在は「株式会社服部管楽器」および関連スクールの代表として、多くの奏者とリペアマンを育成している。
自身の現場経験を活かし、リペア職人の社会的価値向上を目指して活動中。
noteに活動記録あり https://note.com/hattorikangakki
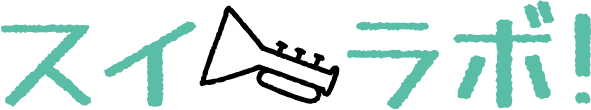

コメント